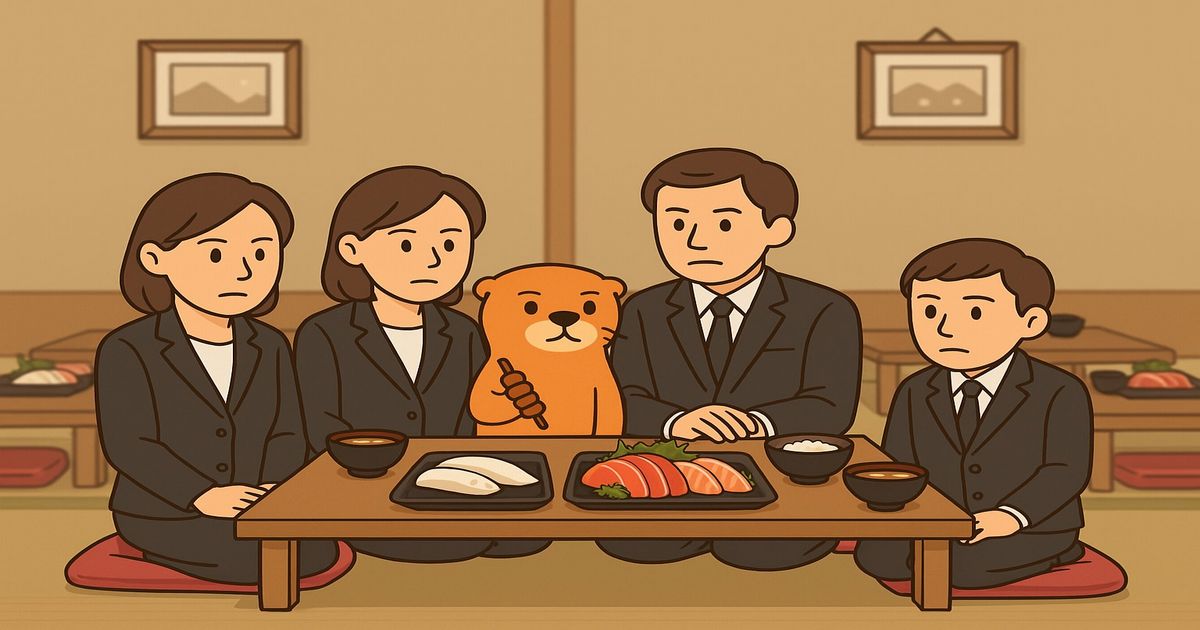📌 この記事の要点
- 函館の活イカ漁が約3週間ぶりに再開(11月12日)
- 全国的豊漁で漁獲枠超過、10月末から休漁していた
- 北海道が「資源調査」名目で特例的に漁を再開
- 価格は例年の3倍、1kg3300円に高騰
- 漁業者は最盛期を逃し「逃がした魚は大きい」と悔しさ
- 上限398tに達すれば再び禁漁、不安が募る
函館名物の活イカ漁が再開:観光客に笑顔戻る
2024年11月12日朝、函館朝市に活気が戻りました。約3週間ぶりに再開された小型船によるスルメイカ漁により、函館名物の「活イカ」が水揚げされたのです。函館朝市駅二市場の活イカ釣り堀には、生きたままのスルメイカが水槽の中で泳ぐ姿が見られ、観光客たちは久しぶりの光景に歓声を上げました。
「活イカ」とは、漁船の水槽から生きたまま水揚げし、水槽付きの専用トラックで市場や飲食店へ運ばれるスルメイカのことです。新鮮さが命で、透明感のある身と甘みが特徴。函館を訪れる観光客にとって、活イカは必食のグルメとして知られています。
長野県から訪れた観光客は「めっちゃおいしい。幸せです」と笑顔を見せ、埼玉県からの観光客も「おいしい。口の中で動く」と活イカならではの食感を楽しんでいました。函館朝市駅二市場の元祖活いか釣堀を営む関係者は「いやー、もううれしいですね。久しぶりの感覚。お客さんも喜んでもらっている」と、再開を喜びました。
函館の観光業にとって、活イカは重要な観光資源です。約3週間の休漁期間中、飲食店や市場は大きな打撃を受けていました。再開によって観光客が戻り、経済活動も活性化し始めています。
休漁の背景:全国的豊漁で漁獲枠超過の矛盾
なぜ函館の活イカ漁は休漁に追い込まれたのでしょうか。その背景には、全国的な豊漁という皮肉な状況がありました。2024年、日本各地でスルメイカが豊漁となり、函館を含む北海道の漁獲量も急増。その結果、国が定める漁獲枠の上限を超えてしまったのです。
日本の漁業では、水産資源を保護するために魚種ごとに漁獲枠が設定されています。スルメイカについても、乱獲を防ぎ資源を持続可能な形で利用するため、年間の漁獲量に上限が設けられています。この制度自体は資源管理の観点から重要ですが、今回のように豊漁年には思わぬ問題を引き起こします。
10月末、北海道全体の漁獲量が上限に達したため、行政は休漁を指示しました。これは法令に基づく措置であり、漁業者は従わざるを得ませんでした。しかし、10月末から11月にかけては、スルメイカの最盛期にあたります。海水温が下がり、イカが沿岸に集まるこの時期は、漁業者にとって最も稼げる「書き入れ時」なのです。
豊漁であるにもかかわらず漁ができない──この矛盾が、漁業者たちを苦しめました。目の前に資源があるのに獲れない。経済的損失は計り知れません。また、函館の観光業にとっても、活イカが提供できないことは大きな痛手でした。この状況を受けて、地元の漁業関係者や自治体から、漁の再開を求める声が高まっていたのです。
「資源調査」名目の特例措置:制度の抜け穴か苦肉の策か
こうした状況を受けて、北海道は特例として「資源調査」の名目で漁の再開を認めました。これにより、約3週間ぶりに活イカ漁が復活したわけですが、この措置には疑問の声も上がっています。
「資源調査」とは本来、魚の生息状況や資源量を把握するための科学的な調査を指します。しかし、今回の措置は実質的に商業漁業の再開であり、「資源調査」という名目は建前に過ぎないのではないかという指摘があります。漁獲されたイカは市場で販売され、観光客が消費する──これは調査というより、明らかに商業活動です。
一方で、この措置を「苦肉の策」と見る意見もあります。漁獲枠という制度の硬直性が、豊漁という恵まれた状況を活かせない矛盾を生んでいる。地域経済と漁業者の生活を守るため、行政が法の範囲内で最大限の配慮をした結果が、この「資源調査」名目の特例だったというわけです。
しかし、問題はこの措置にも上限が設けられていることです。今回の漁獲量の上限は北海道全体で398tとされており、この量に達すればまた禁漁になります。漁業者たちは「いつまで漁ができるのか」という不安を抱えながら、限られた機会を最大限に活かそうと奮闘しているのが現状です。
漁業者の悔しさ「逃がした魚は大きい」
漁の再開を喜ぶ観光客や飲食店とは対照的に、漁業者たちの心中は複雑です。ある漁業者は「再開したのはうれしいんだけども、イカはいなかった。ちょうどいい時期に3週間休んだから…」と、悔しさをにじませました。
この言葉には、漁業者の痛切な思いが込められています。休漁期間中の10月末から11月初旬は、スルメイカの最盛期でした。海水温の低下とともに、大量のイカが沿岸に集まり、漁業者にとっては最も効率よく漁ができる時期です。しかし、この「ゴールデンタイム」に漁ができなかったことで、大きな収入機会を逃してしまいました。
「逃がした魚は大きい」という表現は、まさにこの状況を端的に表しています。最盛期を過ぎた今、イカの群れは既に沖合に移動し始めており、漁獲効率は大幅に低下しています。再開が認められても、かつてのような豊漁は望めないのです。
さらに、今回の特例措置には398tという上限が設けられているため、漁業者たちは「またいつ禁漁になるか分からない」という不安を抱えています。せっかく再開できたのに、わずかな期間で再び操業停止となる可能性があり、経営の見通しが立たない状況が続いています。
価格高騰と経済への影響:例年の3倍、1kg3300円
休漁の影響は、価格にも如実に表れています。函館の市場では11月12日朝、活イカに1kg3300円の値がつきました。これは例年の約3倍という高値です。供給不足と需要の高まりが、この異常な価格高騰を引き起こしています。
通常、スルメイカの価格は1kg1000〜1500円程度です。しかし、約3週間の休漁によって市場への供給が途絶え、在庫が枯渇しました。函館を訪れる観光客は活イカを求めており、飲食店や市場も仕入れを切望していました。この状況下で漁が再開されたため、限られた供給に対して需要が殺到し、価格が急騰したのです。
価格高騰は一見、漁業者にとって有利に見えるかもしれません。しかし実態は異なります。最盛期を逃したことで漁獲量そのものが減少しており、高値で売れても総収入は例年を下回る可能性が高いのです。「量」を失ったことを「単価」では補いきれないのが現実です。
また、価格高騰は消費者や観光業にも影響を与えます。飲食店は仕入れコストが上昇し、メニュー価格に転嫁せざるを得ません。観光客にとっても、活イカを楽しむ費用が高くなり、函館の魅力が損なわれる懸念があります。経済全体で見れば、休漁がもたらした損失は計り知れないのです。
行政と漁業団体の対応:制度の見直しは進むか
今回の事態を受けて、行政や漁業団体の対応が注目されています。北海道庁は「資源調査」名目で特例的に漁を再開させましたが、これは一時的な措置に過ぎません。根本的な問題解決には、漁獲枠制度そのものの見直しが必要だという声が高まっています。
漁獲枠制度は、水産資源の持続可能な利用を目的としています。乱獲を防ぎ、将来世代にも豊かな海を残すという理念は正しいものです。しかし、今回のケースのように、豊漁年に最盛期の漁を禁止するという硬直的な運用は、制度の目的と矛盾しているのではないかという指摘があります。
漁業関係者からは、「豊漁年には漁獲枠を柔軟に調整すべき」「地域ごとの事情を考慮した運用が必要」といった意見が出ています。また、「資源調査」という名目での商業漁業を認めるくらいなら、最初から制度を見直すべきだという批判的な声もあります。
一方、水産庁や研究機関は、資源管理の重要性を強調しています。短期的な経済利益を優先して乱獲すれば、将来的に資源が枯渇し、漁業そのものが成り立たなくなるリスクがあるというわけです。この主張も一理ありますが、現場の漁業者にとっては「目の前の生活」が最優先事項であり、理念と現実のギャップが埋まらない状況が続いています。
専門家の見解:資源管理と地域経済の両立は可能か
水産資源管理の専門家は、今回の事態をどう見ているのでしょうか。多くの専門家は、「資源管理と地域経済の両立」という難しい課題に直面していると指摘しています。
ある水産学者は「漁獲枠制度は必要だが、運用に柔軟性を持たせるべき」と述べています。豊漁年と不漁年で同じ上限を適用するのではなく、資源量に応じて枠を調整する「動的管理」が必要だというのです。科学的なデータに基づいて資源量を評価し、余裕がある年には漁獲枠を増やす──このような仕組みがあれば、今回のような矛盾は避けられたかもしれません。
また、別の専門家は「地域の特性を考慮した制度設計が重要」と指摘します。函館の活イカ漁は、単なる漁業ではなく観光資源でもあります。地域経済への影響が大きい特殊なケースでは、全国一律の基準ではなく、地域の実情に合わせた特例措置を制度として認めるべきだという意見です。
一方で、「短期的な経済利益を優先すれば、長期的には資源が枯渇する」という警告も忘れてはなりません。過去には乱獲によって漁業資源が激減し、漁業そのものが衰退した例が数多くあります。今回の措置が前例となって、資源管理が形骸化することへの懸念も根強くあります。資源保護と経済活動のバランスをどう取るか──これは日本の漁業全体が抱える根本的な課題なのです。
SNSと世間の反応:賛否両論が交錯
函館の活イカ漁再開のニュースは、SNS上でも大きな反響を呼んでいます。観光客や函館ファンからは喜びの声が上がる一方で、制度への疑問や漁業者への同情の声も多数寄せられています。
「函館に活イカが戻ってきて嬉しい!」「来月行くから間に合って良かった」「函館の活イカは最高」といった、再開を歓迎するコメントが数多く投稿されています。観光客にとって、活イカは函館旅行の大きな楽しみであり、その復活は純粋に喜ばしいニュースなのです。
一方で、「資源調査って名目がおかしい」「実質的に商業漁業なのに調査って言い張るのは問題では」「制度の抜け穴を使っているように見える」といった、特例措置への批判的な意見も見られます。法の精神を守りながら柔軟に対応することと、制度を骨抜きにすることの境界線はどこにあるのか──多くの人が疑問を抱いています。
また、「漁業者が気の毒」「最盛期に漁ができないなんて理不尽」「豊漁なのに獲れないって矛盾してる」といった、漁業者への同情の声も多数上がっています。ルールを守って休漁したのに経済的損失を被り、再開しても最盛期は過ぎている──この不条理な状況に、多くの人が共感を寄せているのです。
今後の見通し:上限398tの壁と再禁漁の不安
今回の特例措置による漁の再開は、決して問題の根本的解決ではありません。北海道全体で398tという上限が設けられており、この量に達すれば再び禁漁となります。漁業者たちは「いつまで漁ができるのか」という不安を抱えながら、日々操業しています。
398tという数字は、決して多くはありません。順調に漁が進めば、数週間で上限に達する可能性があります。そうなれば、再び函館から活イカが消え、観光客はがっかりし、漁業者は収入を失います。この不安定な状況が、地域経済に暗い影を落としています。
長期的な視点で見れば、漁獲枠制度そのものの見直しが不可欠です。豊漁年と不漁年で柔軟に上限を調整する仕組み、地域の特性を考慮した特例措置の制度化、科学的データに基づく動的な資源管理──こうした改革が進まなければ、同じ問題が繰り返されるでしょう。
また、函館の活イカに依存しすぎない観光戦略も必要かもしれません。活イカは確かに魅力的な観光資源ですが、自然相手の漁業である以上、安定供給は保証されません。他の魅力を開発し、多様な観光資源を持つことが、地域経済の安定につながるのではないでしょうか。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1: なぜ豊漁なのに休漁になったのですか?
A: 全国的な豊漁により、国が定める年間の漁獲枠上限を超えてしまったためです。水産資源を保護し持続可能な漁業を実現するため、上限に達すると休漁が命じられる制度になっています。
Q2: 「資源調査」名目での漁再開は適切ですか?
A: 賛否両論があります。地域経済と漁業者を守るための苦肉の策という見方がある一方で、実質的に商業漁業なのに「調査」と称することへの疑問の声もあります。制度の抜け穴を使っているとの批判もあり、議論が続いています。
Q3: 活イカの価格が例年の3倍になった理由は?
A: 約3週間の休漁により供給が途絶え、市場の在庫が枯渇したためです。函館を訪れる観光客や飲食店からの需要は高いまま維持されていたため、限られた供給に対して需要が殺到し、価格が急騰しました。
Q4: 漁業者が「逃がした魚は大きい」と言う理由は?
A: 休漁期間中の10月末〜11月初旬がスルメイカの最盛期だったためです。最も効率よく漁ができる時期に操業できず、大きな収入機会を逃してしまいました。再開後はイカの群れが沖合に移動し、漁獲効率が大幅に低下しています。
Q5: 今後また禁漁になる可能性はありますか?
A: はい、可能性は高いです。今回の特例措置には北海道全体で398tという上限が設けられており、この量に達すれば再び禁漁となります。数週間で上限に達する可能性があり、漁業者は不安を抱えながら操業しています。
📝 まとめ:制度と現実のギャップが浮き彫りに
函館の名物・活イカ漁が約3週間ぶりに再開されましたが、その背景には複雑な問題が潜んでいます。全国的な豊漁で漁獲枠を超過し、最盛期に休漁を強いられた漁業者は「逃がした魚は大きい」と悔しさをにじませています。北海道が「資源調査」名目で特例的に漁を再開したものの、実質的には商業漁業であり、制度の矛盾が浮き彫りになりました。
価格は例年の3倍となる1kg3300円に高騰し、観光客は活イカの復活を喜んでいますが、上限398tに達すれば再び禁漁。漁業者の不安は消えず、地域経済への影響も懸念されます。資源管理の重要性は理解できるものの、豊漁なのに獲れないという矛盾、最盛期を逃した経済的損失──制度の硬直性が現場に大きな負担を強いている現実があります。
資源管理と地域経済の両立は可能なのか。豊漁年には柔軟に漁獲枠を調整する動的管理、地域の特性を考慮した制度設計──根本的な見直しが求められています。函館の活イカ漁をめぐる問題は、日本の漁業全体が抱える課題の縮図と言えるでしょう。