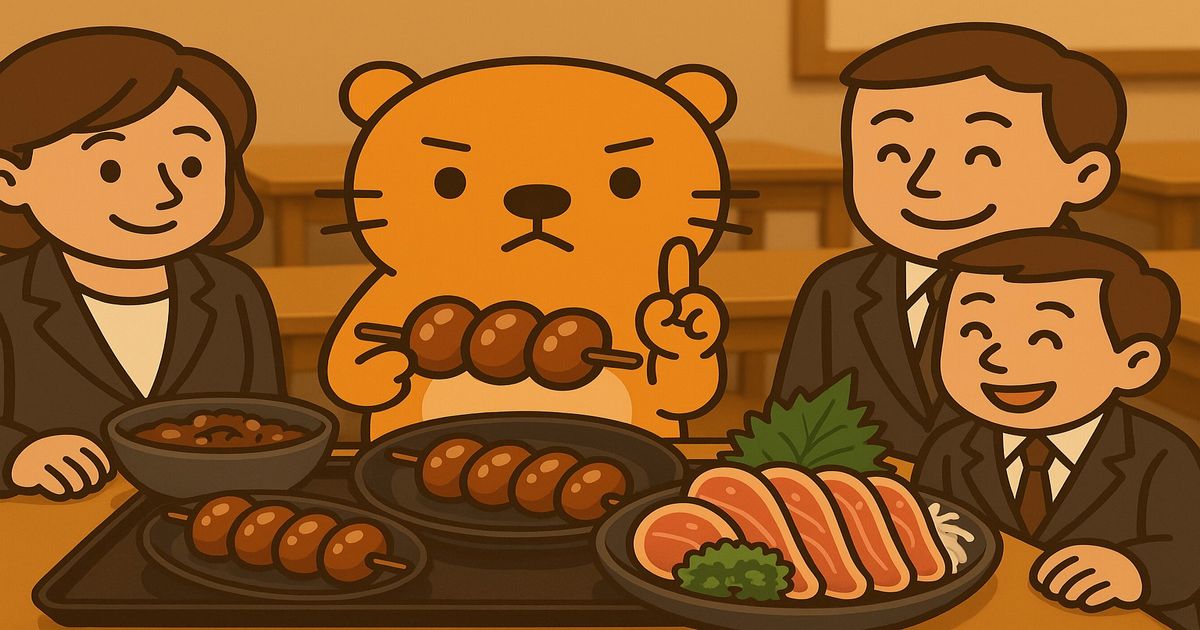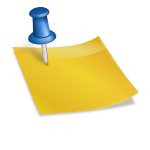コメ価格の高騰、材料費の上昇、人手不足——。そんな逆風の中、全国の「すし店」が意外な追い風を受けています。
東京商工リサーチの最新調査によると、2025年1〜10月のすし店の倒産件数が前年同期比で約3割減少。
3年連続で増加していた倒産が一転して減少に転じた背景には、訪日観光客による“インバウンド特需”がありました。
なぜ、物価高の中でも寿司業界は持ちこたえたのでしょうか。あなたも気になりませんか?
ニュース本編|倒産が減少に転じた理由
東京商工リサーチのまとめでは、2025年1〜10月の「すし店」倒産(負債1,000万円以上)は全国で17件。前年同期(24件)から約3割の減少となりました。
これまで3年連続で増加していたすし店倒産ですが、今年はようやく歯止めがかかった形です。背景には、外国人観光客の増加による売上回復が挙げられます。
訪日外国人は2025年9月までに累計3,000万人を突破。特に寿司は人気の高い日本食であり、都内や地方都市の店でも予約が取りにくい状況が続いています。
背景|高騰する食材と続く人手不足
コメや魚介類などの仕入れコストは依然として高止まりしています。職人不足や人件費の上昇も止まらず、経営を圧迫しているのが現状です。
中小規模のすし店では、価格転嫁が難しい一方、大手チェーンではメニューの見直しやAIによる需給管理などで効率化を進めています。
こうした「構造的な差」が、すし店業界全体の二極化を生んでいるといえるでしょう。
関連比較|回転寿司チェーンの好調
スシローを運営するFOOD & LIFE COMPANIESは、2025年度第3四半期の国内事業売上高が前年同期比11.6%増の1,959億円。くら寿司も同1.8%増の1,324億円と堅調でした。
これら大手チェーンは、インバウンド向けメニューや自動化システムを導入し、外国人観光客のニーズをうまく取り込んでいます。
一方、個人経営のすし店は原価高に苦しみながらも、地元密着型の営業で生き残りを図っています。
目撃談・現場の声|予約殺到する人気店も
東京都内のある人気すし店では、9割以上の予約が外国人観光客という日もあるといいます。
「仕入れを事前予約制にすることで、食材ロスを減らし、原価を抑えています」と店主。
また、地方でも観光地近くの店舗が復調しており、「英語メニュー」や「QR注文」など、柔軟な対応を行う店ほど売上が安定している傾向が見られます。
芸能界との意外なつながり
近年、寿司職人をテーマにしたドラマや映画が増え、寿司文化への関心が高まっています。
特にNetflix作品や地上波ドラマで描かれる「カウンターの世界」は、若年層の関心を集め、観光客の“体験消費”にもつながっているようです。
芸能界の影響が業界の回復を後押ししているのも、2025年の特徴といえるでしょう。
SNSの反応|「寿司の力すごい」「外国人多すぎ」
X(旧Twitter)やInstagramでは、「近所の寿司屋、外国人で満席」「すし文化が守られてうれしい」といった投稿が目立ちます。
一方で、「地元民が入れない」「値上げがつらい」といった声もあり、インバウンド依存のリスクも指摘されています。
今後の展望|“すし店サバイバル”は続く
倒産件数が減少したとはいえ、業界が完全に安定したわけではありません。
インバウンド需要が落ち着けば、再び厳しい経営環境に直面する可能性もあります。
中長期的には、地域密着・外国語対応・食材の地産地消といった「持続可能なすし経営」が鍵となるでしょう。
・2025年1〜10月のすし店倒産は17件(約3割減)
・訪日客増で売上が回復、原価上昇を吸収
・大手チェーンは自動化と多言語化で好調
・地方の個人店も工夫次第で復調の兆し
Q:なぜ2025年のすし店倒産が減ったのですか?
A:訪日外国人の増加による売上拡大が大きな要因です。原材料費の上昇をカバーできた店が多くありました。
Q:今後のすし業界はどうなる?
A:インバウンド頼みからの脱却が課題です。地域密着型や地産地消へのシフトが注目されています。
すし店倒産が減少した裏には、海外からの観光客という“救いの手”がありました。
しかし、円安や物価高、人材難といった根本的な課題は残ったままです。
今後も「すし文化」を守るためには、観光需要に頼らず、地域と共に生きる経営が求められるでしょう。